日本とイタリア150年の揺るぎない友情
ナポリ東洋大学 日本史・日本政治学科 ノエミ・ランナ准教授
1866年8月25日、日本とイタリアは、「日本大君と伊太利國王其親族並に世々」とその相互の所領臣民との間で「無差別」に、「永久の平和懇親」を願って修好通商条約を締結しました。第1条に述べられたこの願いは現実のものとなり、条約への署名から150年にわたり、日伊両国は絶えず友好的な関係を維持しています。
国交開設後、両国の関心は様々な要因によりかなりの共通性を帯びるようになりました。まず、日本とイタリアは貿易の面で相互補完的な関係にありました。養蚕業が主な産業の一つであったイタリアは、1854年より、国内のほとんどの養蚕地区に広がった蚕の伝染病によって大きな打撃を受けていました。この伝染病は他の欧州諸国にも蔓延していたため、イタリアの業者は日本の蚕卵市場へ目を向けるようになります。一方、日本にとってもイタリアからの需要は大きな収入源となり、江戸時代(1603~1868)末期から明治時代(1868~1912年)初期にかけ、統計上、イタリアは多い年には日本の輸出先の2割にも達していました。また、両国民間の深い相互理解は、貿易上の理由に加え、イタリア統一運動により生み出されたイタリアに対する共感にもよるものでした。日本人の目からすれば、イタリアにおける統一運動は、ほぼ同時期に起こった江戸幕府の終焉、そして明治維新(1868年)につながる歴史的な出来事と非常に似通っているように見えたのです。
これらを踏まえれば、イタリアの軍艦ヴェットール・ピサニが、1881年、外国船として史上初めて天皇陛下をお迎えしたことも不思議ではありません。とはいえ、この極めて良好な二国間関係は、これに8年先立つ岩倉使節団(1871~1873年)のイタリア訪問に際して既に確固たるものとなっていました。欧米諸国に向けて日本を出港した外交使節団は、新しい日本政府の信任状を訪問先の国々に捧呈し、また、それら諸国の政治・経済・法制度を直に学ぶという2つの目的を掲げていました。この使節団は、1873年5月9日から6月3日にかけイタリアに滞在し、様々な都市を訪問しました。その後は、1888年に日伊学会が発足し、両国文化の相互理解に大きな推進力を与えていくことになります。
第一次世界大戦では、日本とイタリアの両国は、イギリス・フランス・ロシアの三国協商側につきます。平和条約締結後も、両国は同じ道を歩みました。終戦直後の理想主義に満ちた風潮の中、日伊両政府の距離は更に縮まります。たとえば、1920年に皇太子殿下(後の昭和天皇)がイタリアを御訪問されたことは象徴的なことですし、同年にイタリア人パイロット2名が史上初めてローマから東京に飛行したことは実質的な例として挙げることができます。残念ながら、防共協定(1937年)と日独伊三国同盟(1940年)が示すように、両国は、自由民主主義の危機を招き軍事的な拡張政策をもたらした不吉な時代の流れも共に歩むこととなりました。
1945年は、日本とイタリアにとって新たな出発点となりました。両国の歩みは改めて交差するようになります。新しいイタリア共和国は、反ファシズム、レジスタンス運動、国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄、といった民主主義的な価値観を基本として成り立っています。また日本は、民主主義と平和主義を復興の土台としました。概して、冷戦時代は両国にとって実りある時期となりました。政治対話は最も高いレベルにまで達し、貿易量も次第に伸びていきました。1962年に設立されたローマ日本文化会館や1959年に東京で再度開館したイタリア文化会館による価値ある活動を通じて、文化面の交流も活発化しました。また、多くの奨学金は、両国の若い世代の学者たちに交流の機会をもたらし、まさに大陸を横断する学問共同体を生み出したと言うことができます。
両国間に友好と平和が維持されてきたことには、様々な要素が寄与しています。まず思い起こすべきことは、修好通商条約の締結(1866年)以前に、両国間には先程述べたイタリア養蚕業者による商いだけではなく、16世紀に遡る多くの重要な出会いがあったということです。まさに今年は、支倉常長が率いる使節団が1613年に仙台を出港し、ローマに到着してから400周年に当たり、その記念式典が行われました。「イタリア・日本の450年」(「Italia-Giappone 450 anni」、アドルフォ・タンブレッロ教授監修)に掲載された数々の論文において事細かに裏打ちされているとおり(詳細は同書に譲ります)、日伊関係は長い歴史を誇り、両国の政治・経済・文化など様々な場面に影響を与えてきました。
第二は、日伊関係が発展してきた国際環境は、二国間関係に良い意味での影響を与えてきたということです。修好通商条約が締結された19世紀の後半、日本とイタリアは新参者、すなわち、両国は、当時の国際秩序を支配していた大国と比べれば、近代化の道を遅れて歩み始めた国でした。そのため、両政府は、同じ国際システムの縛りに対峙しなければならず、したがって、国際社会において(主要国としての)威信と認知を得るという共通の目標を追い求めていました。また、国際秩序が二極構造となった1945年以降には、日本とイタリアは再び類似の課題に挑むことになります。世界が東西ブロックに明確に分断された中で、戦争により相当な被害を受けていた経済システムの早期回復を阻害することなく、自国領域の安全を確保することが最優先事項となりました。ここでも両国は同様の道を選び、米国に歩調を合わせることで、地理的な特徴という利点を最大限に活かしつつ、国民に平和と繁栄を保障することに成功しました。現在でも、日本とイタリアは相互に深い絆で結ばれ、共に歩み続けています。
注)本寄稿文の内容は、政府の見解を示すものではありません。
国交開設後、両国の関心は様々な要因によりかなりの共通性を帯びるようになりました。まず、日本とイタリアは貿易の面で相互補完的な関係にありました。養蚕業が主な産業の一つであったイタリアは、1854年より、国内のほとんどの養蚕地区に広がった蚕の伝染病によって大きな打撃を受けていました。この伝染病は他の欧州諸国にも蔓延していたため、イタリアの業者は日本の蚕卵市場へ目を向けるようになります。一方、日本にとってもイタリアからの需要は大きな収入源となり、江戸時代(1603~1868)末期から明治時代(1868~1912年)初期にかけ、統計上、イタリアは多い年には日本の輸出先の2割にも達していました。また、両国民間の深い相互理解は、貿易上の理由に加え、イタリア統一運動により生み出されたイタリアに対する共感にもよるものでした。日本人の目からすれば、イタリアにおける統一運動は、ほぼ同時期に起こった江戸幕府の終焉、そして明治維新(1868年)につながる歴史的な出来事と非常に似通っているように見えたのです。
これらを踏まえれば、イタリアの軍艦ヴェットール・ピサニが、1881年、外国船として史上初めて天皇陛下をお迎えしたことも不思議ではありません。とはいえ、この極めて良好な二国間関係は、これに8年先立つ岩倉使節団(1871~1873年)のイタリア訪問に際して既に確固たるものとなっていました。欧米諸国に向けて日本を出港した外交使節団は、新しい日本政府の信任状を訪問先の国々に捧呈し、また、それら諸国の政治・経済・法制度を直に学ぶという2つの目的を掲げていました。この使節団は、1873年5月9日から6月3日にかけイタリアに滞在し、様々な都市を訪問しました。その後は、1888年に日伊学会が発足し、両国文化の相互理解に大きな推進力を与えていくことになります。
第一次世界大戦では、日本とイタリアの両国は、イギリス・フランス・ロシアの三国協商側につきます。平和条約締結後も、両国は同じ道を歩みました。終戦直後の理想主義に満ちた風潮の中、日伊両政府の距離は更に縮まります。たとえば、1920年に皇太子殿下(後の昭和天皇)がイタリアを御訪問されたことは象徴的なことですし、同年にイタリア人パイロット2名が史上初めてローマから東京に飛行したことは実質的な例として挙げることができます。残念ながら、防共協定(1937年)と日独伊三国同盟(1940年)が示すように、両国は、自由民主主義の危機を招き軍事的な拡張政策をもたらした不吉な時代の流れも共に歩むこととなりました。
1945年は、日本とイタリアにとって新たな出発点となりました。両国の歩みは改めて交差するようになります。新しいイタリア共和国は、反ファシズム、レジスタンス運動、国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄、といった民主主義的な価値観を基本として成り立っています。また日本は、民主主義と平和主義を復興の土台としました。概して、冷戦時代は両国にとって実りある時期となりました。政治対話は最も高いレベルにまで達し、貿易量も次第に伸びていきました。1962年に設立されたローマ日本文化会館や1959年に東京で再度開館したイタリア文化会館による価値ある活動を通じて、文化面の交流も活発化しました。また、多くの奨学金は、両国の若い世代の学者たちに交流の機会をもたらし、まさに大陸を横断する学問共同体を生み出したと言うことができます。
両国間に友好と平和が維持されてきたことには、様々な要素が寄与しています。まず思い起こすべきことは、修好通商条約の締結(1866年)以前に、両国間には先程述べたイタリア養蚕業者による商いだけではなく、16世紀に遡る多くの重要な出会いがあったということです。まさに今年は、支倉常長が率いる使節団が1613年に仙台を出港し、ローマに到着してから400周年に当たり、その記念式典が行われました。「イタリア・日本の450年」(「Italia-Giappone 450 anni」、アドルフォ・タンブレッロ教授監修)に掲載された数々の論文において事細かに裏打ちされているとおり(詳細は同書に譲ります)、日伊関係は長い歴史を誇り、両国の政治・経済・文化など様々な場面に影響を与えてきました。
第二は、日伊関係が発展してきた国際環境は、二国間関係に良い意味での影響を与えてきたということです。修好通商条約が締結された19世紀の後半、日本とイタリアは新参者、すなわち、両国は、当時の国際秩序を支配していた大国と比べれば、近代化の道を遅れて歩み始めた国でした。そのため、両政府は、同じ国際システムの縛りに対峙しなければならず、したがって、国際社会において(主要国としての)威信と認知を得るという共通の目標を追い求めていました。また、国際秩序が二極構造となった1945年以降には、日本とイタリアは再び類似の課題に挑むことになります。世界が東西ブロックに明確に分断された中で、戦争により相当な被害を受けていた経済システムの早期回復を阻害することなく、自国領域の安全を確保することが最優先事項となりました。ここでも両国は同様の道を選び、米国に歩調を合わせることで、地理的な特徴という利点を最大限に活かしつつ、国民に平和と繁栄を保障することに成功しました。現在でも、日本とイタリアは相互に深い絆で結ばれ、共に歩み続けています。
注)本寄稿文の内容は、政府の見解を示すものではありません。
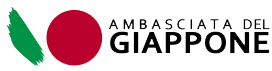
 ITALIANO/イタリア語
ITALIANO/イタリア語